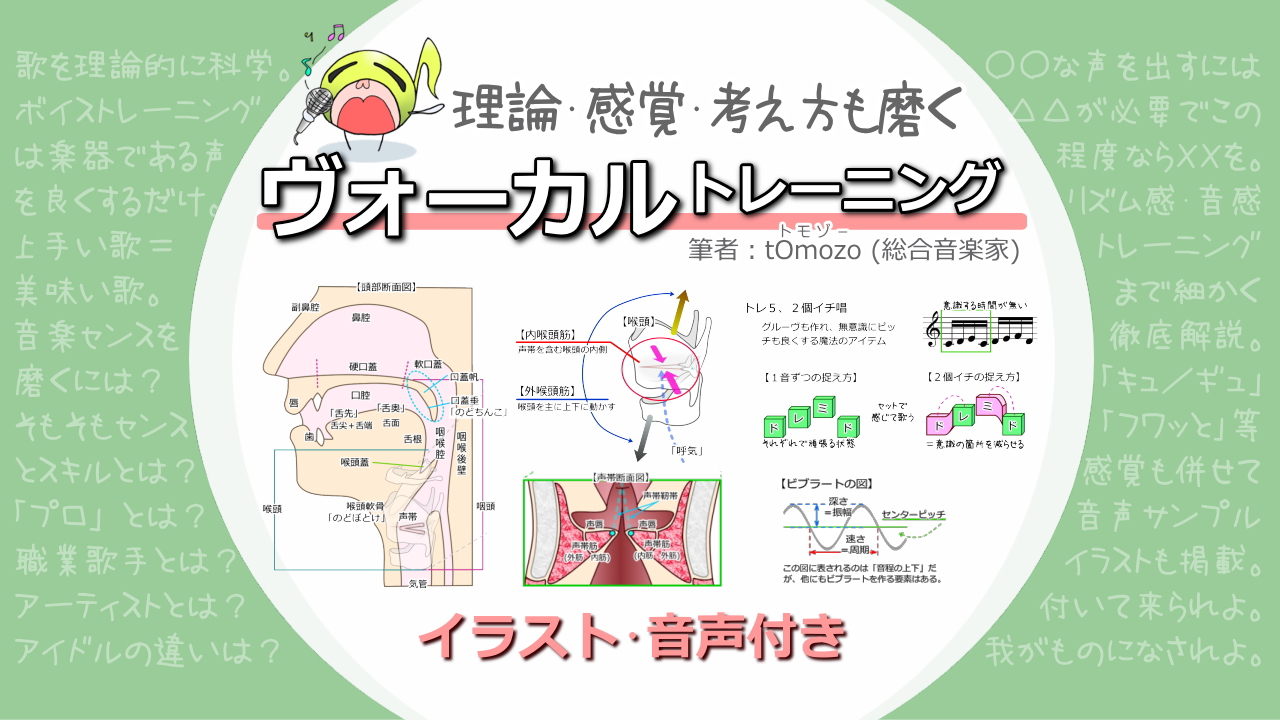取材・文:藤井 徹(Vocal Magazine Web)
国内屈指の男性ヴォーカル・デュオ、CHEMISTRYから、大人の魅力がたっぷり味わえるミニ・アルバム『BLUE CHEMISTRY』が届けられた。
タイトルに付けられた「青=BLUE」は、ジャズミュージックを象徴する色で、本作はジャズテイストのアレンジが施されたカバー曲なども収録されており、そこにふたりの芳醇な声が溶け合った極上の音が吹き込まれている。
Vocal Magazine Web初登場となる彼らに、ヴォーカリストとしてのルーツや、デュオならではのハーモニーなど、多岐にわたって質問を投げかけてみた。
※インタビューの最後に素敵なプレゼントがあります。お楽しみに。
歌い方は常にライブの本番で試していますね(川畑)
──Vocal Magazine Web初登場ということで、おふたりのシンガーとしての原点、ルーツについて聞かせてください。
川畑要 子供の頃から人前で歌うのが大好きでしたね。中1の頃はX JAPANが好きでライブにも行きました。あとは兄の影響もあってZIGGYさんやBOØWYさんを聴いてたりして……。兄はギターを弾いていて、僕も中1のときにお年玉をはたいてベースを買ったんですが、当時はベースの音が聴こえないから全然面白くなくて……今はベース大好きなんですけど(笑)。ヴォーカリストとして「歌っていいな、歌手になりたいな」と思ったのは15歳の頃、やっぱり尾崎豊さんの影響が大きかったですね。その後に友達とコピーバンドを組んだときもヴォーカルでした。
堂珍嘉邦 原点という意味では幼少時に童謡とか歌っていたと思うんですが、その後は人前ではほぼ歌えなかったですね。思春期特有のものですが、いろんなコンプレックスもありつつで、友達はいたんだけど、表に出るとき肝心の自分の身体を使って声を出すっていうところが「絶対恥ずかしくて無理!」ってなってたんですよ。初めて人前で歌ったのは、アメリカへホームステイに行ったとき。そこで褒められてからは日本人の前でも歌えるようになりました。
──アメリカで歌ったのは、洋楽ですか?
堂珍 はい、MR.BIGの「To Be With You」です。一緒に行った友達がギターを弾いて僕が歌ったんですけど、友達がいたから僕もちょっと声を出すことができた……みたいな感じですね。そこで褒められて、それで調子に乗って帰国してから「じゃあバンド入る」って。
──「こういう風に歌いたい」と真似したシンガーは?
川畑 実は目標にした歌い方はないんですが、アーティストさんを聴いて歌ったときには、毎回モノマネみたいになっていたと思うんです。尾崎さんを聴いたら尾崎さんっぽい歌い方になるし、B’zさんなら稲葉(浩志)さんっぽく歌っていただろうし、ザ・ブルーハーツさんなら、甲本(ヒロト)さん、みたいな。デビューしてからも「自分の声、オリジナルって何なんだろう?」って思うところもありましたよ。それが見つかる……いつ見つかったかも覚えてないんですけど(笑)、1枚、2枚とCDを出してから「俺ってこれでいいんだ」みたいなことが見つかった感じなので、コレという見本はなかったかなあ。
──その都度、全力でその人の歌い方を吸収していたんですね。
川畑 そうですね。たぶん、どこかは似ていたんだと思います。ずっとサザンオールスターズが好きな人って、桑田(佳祐)さんっぽい歌い方だし、矢沢永吉さんが大好きな人も、やっぱり矢沢さんじゃないですか。なので、プロになってからは、そういう部分から早く抜けたかったんです。「きっと俺の歌も、モノマネっぽくなっちゃってるのかな」とか。自分でもわかんないんですけど、きっとそういう技術とか特徴のある部分を真似したっていうのはありましたよね。
堂珍 (川畑)要は上田正樹さんとか、そうじゃない?
川畑 上田正樹さんを聴いたのは18歳くらいだからね。影響っていうよりは、「現場の先輩が歌ってた」みたいな。自分と同じようなガラッガラの声をした人が歌っていて、ああカッコいいなって……。
堂珍 この間テレビの音楽番組に出たときに要が紹介してたんですよ。もちろん僕も存在は知ってたけど、ちゃんと観たり聴いたりしたことはなかったので、家に帰ってYouTubeで上田さんのライブパフォーマンスを観たら、「あ、けっこう好きかも」って。上田さんの声、超ナチュラルなんですよ。「これ、ちょっといただきます」じゃないけど、自分たちと近いものがあるなと。
川畑 あの映像のメロディとか、オリジナルのCDとは、ほぼ違うからね。でも今でもカッコいい!みたいな。
──「悲しい色やね」ですか?
川畑 「わがまま」です。あの曲が好きで。
堂珍 ご自身はマイクしか持たれてないんだけど、そのステージの中での佇まいがとてもカッコよかったですね。
──おふたりはオーディション番組『ASAYAN』を経てデビューしたわけですが、初期の頃にボイストレーニングなどは受けましたか?
川畑 オーディションのとき、一回ボイトレあったよね。
堂珍 僕らがCHEMISTRYになる前に「最後の夜」っていう曲で「仮デビュー」したんですが(注:「ASAYAN超男子。川畑・堂珍」の名義)、そのときにボイストレーナーの方に付いていただいて何回かレッスンしたはずです。そのあとはそれぞれ個人的にボイトレの先生に見てもらったりしましたけど、継続的にCHEMISTRYとして続けているボイトレっていうのはないですね。
川畑 いろいろやってみたんだけど、正直あんまり(効果が)わからないなと思ってたんです。で、僕が一番好きなのはブラックミュージックだから、これは黒人の先生に習うのが一番早いかもしれないと紹介してもらった方に一番長く習いました。歌い方、モチベーションもそうだし、歌への考え方や向き合い方が劇的に変わりましたね。でも、それ以降ボイトレは何十年もやってないです。
堂珍 クラシック系、ブラックの人などのレッスンを2〜3回ずつ受けたんですが、やっぱり通うのが大変だなとか、レッスン料が高いなとか(笑)。まあ、いろいろあったんですけど、「共通して言ってることはこういうことなのかな」と自分の中で理解してからはやってないですね。ただ、ついつい忘れがちになっていることがあるときは、レッスンをやっている友達や後輩に電話で聞いたりします。実際この前、zoom(オンライン)で久々にレッスンをやりました。「ライブでこの部分がちょっと出づらいんだけど、たぶん意識の仕方が悪いというか、どこか忘れちゃっていて、どうしたらいいかな?」と。
──プロの方の中には、日常的なメンテナンスとしてボイトレを受ける方もいますね。
川畑 そうでしょうね。あとはメンタル面が強いんじゃないかなって最近すごく思います。学校へ行ってる人とかボイトレを受ける人は、「これがないとメンタル的に安定しない」っていうところのケアも含まれてるのかなって。僕はずっとパーソナルトレーナーについてもらってワークアウトをやってるんで、全部それで補ってます。さっきの黒人のボイストレーナーさんが言っていた「身体が鳴る」って言葉がずっと頭に残ってるんですよね。「身体をスピーカーと思え」とか、「リラックスしろ」とか……。今はボイトレじゃないけれど、違うところ(ジム)でやってます。
──当時、ヴォーカルのディレクションに関して、決まった方はいらしたんですか?
川畑 初期は和田昌哉さんが曲も書いてくださっていますし、ディレクションをしてくれましたね。
──お互いの声や歌い方について、言葉で擦り合わせることなどはありますか?
堂珍 あんまり話はしないかもしれませんね。
川畑 和田さんがディレクションに入っていて、まずそこに信頼関係がありましたからね。交互にレコーディングブースへ入る中で、歌い方のバランス面もそうですし、語尾なんかも「これぐらいで切ったほうがいい」っていう長さに合わせてハモったりして。本当に和田さんには鍛えてもらった感じがしますね。

 メールマガジンを購読
メールマガジンを購読