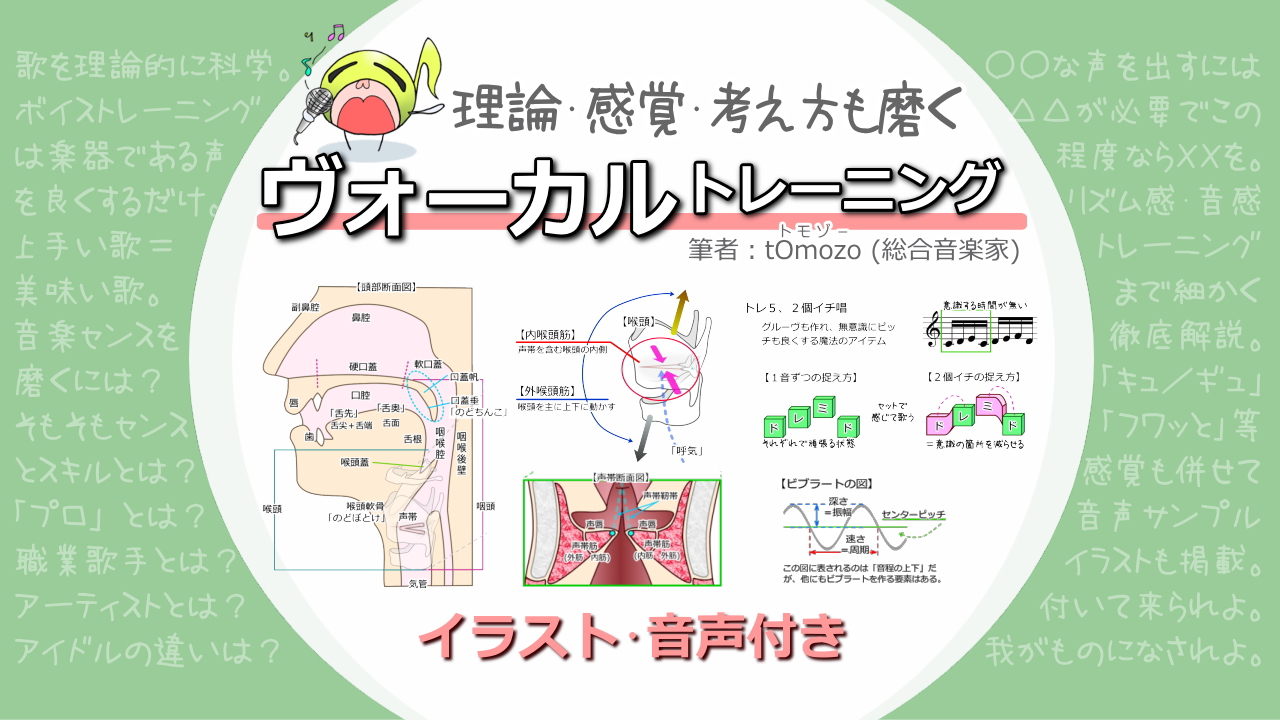【インタビュー】川崎鷹也、新曲「Be yourself」制作と、自身のヴォーカルスタイルを作り上げた“こだわり”を語る!
2022.01.25
取材・文:藤井 徹(Vocal Magazine web)
撮影:上溝恭香(2021年12月18日(土)東京・ヒューリックホール東京)
本当にことあるごとにビブラートを使う少年だったんですよ。
──川崎さんは、“ビブラートがすごい!”と定評があるんですけど、この曲でも《幾千の時を超えて》っていう部分を始め、音程を上げてみたり、強くして弱くしてみたりとか、音量レベルを調節しながらビブラートをつけていて、多くのパターン持っているように感じます。録音する際に、何パターンかビブラートを試したりしますか?
川崎 技術的な使い分けはしないですが、ニュアンス的な部分で言葉の乗せ方のアプローチはいろいろチャレンジしていますね。例えば“泣き声”じゃないけど、はっきりとした強めの口調じゃなくて、ちょっと音としてはブレるんですけど感情が乗る歌い方だったり。ほかにも“優しく歌う”などのテイクは何個もあって、それに沿ったビブラート(の使い方)になってるだけなのかなと思います。ビブラートを中心で僕は考えたことはないので、優しく歌ったら優しいビブラートになるだけだし、力強く歌ったら、力強いビブラートになる。その中で“ここの言葉は語尾をプッシュしよう”とかっていう意識はあるので、そういうビブラートになっているのかもしれないですね。
──あくまで感情や表現力優先でやっていらっしゃるんですね。
川崎 気持ちよく歌った結果な感じですね。いろんな曲を聴いて、いろんな歌い方をしてやってきた下積みが、今になってやっと活きてきた気はします。
──誰かのビブラートを真似して練習した経験はあるんですか?
川崎 つんく♂さんですね。小学生、中学生の頃、あのビブラートがやりたくて「シングルベッド」を死ぬほど歌ってました。《♪シングルぅ〜〜〜ベぇぇッ〜〜〜ド》って。あとはGACKTさんですね。「野に咲く花のように」の《♪誰もいないグラウンドのぉ〜〜〜〜》、この幅を気持ちいいなと思ってました(笑)。本当にことあるごとにビブラートを使う少年だったんですよ。学校から帰ってきたときも「ただいまぁぁ〜〜〜〜」って言ってましたからね(笑)。
──これは貴重なお話ですね! この曲の歌詞では一人称複数の《僕ら》ですよね。リリースしている音源だと初めてですか?
川崎 ラブソングでは《2人》とか《僕ら》とかっていう表現をするんですけど、ラブソングではない中での《僕ら》っていう表現は、確かにないかもしれないですね。
──あえて《僕ら》としたのは、ドラマのいわゆる友情という部分を伝えたいという想いから?
川崎 本当にその通りです。主人公がいて、その周りにはいろんな仲間がいてという情景を思い浮かべながら書いた曲でもあるので、一人称は《僕ら》なのかなと。
──今までと違ったテイストの楽曲が生まれたことで、“2022年の川崎鷹也”に対して、自分で楽しみにしてる部分はありますか?
川崎 ここ1〜2年、ライブでのバンドメンバーなど新しく出会う人が急激に増えているんです。出会いがあればあるほど、僕の脳みそだけじゃ表現できないアイディアだったり、自分以外のエッセンスを新たに加えることができているので、そういったワクワク感がありますね。僕ひとりではこんなアレンジは絶対できないので、そういった意味で2022年は、新たな仲間と一緒にひとつの音を作り上げていくチャレンジで、よりいろんな川崎鷹也が見せられるのかなと思っています。
──昨年12月に、ヒューリックホール東京公演でのMCで、今の状況を“ロールプレイングゲームみたいだ”と話してましたね。
川崎 はい。自分が主人公というのもおこがましいですし、それこそ(ライブは)一緒に誰かと戦ったわけじゃないですけど、ひとりひとりに楽器という武器があって、気づいたらどんどん仲間になっていって……。そういう意味でRPGのドラクエみたいな感じはしますね(笑)。
──バンドスタイルでのライブは何回か経験が?
川崎 1回だけやったことありますね。2020年12月に渋谷O-EASTで。
──アルバム『カレンダー』が本格的なバンドレコーディングで、そのツアーでバンドスタイルでやるというのは、ほぼ、初のお披露目だったんですね。弾き語りとはまた違った面を見せてもらえましたが、自身の手応えは?
川崎 すごくありました。アコースティックギターでのライブはもちろん僕のスタイルですし楽しいんですが、やっぱりバンドなので音圧がそもそも違いますしね。弾き語りではイヤモニを基本的には付けてなかったけど、今回は付けていたりしますし、その音のバランスも含めて“自分の実力以上のものが出たライブだったな”と振り返って思っているところです。もちろん“ソールドアウトした皆さんに満足して帰ってもらいたい、ここに来てよかったと思ってもらいたい”ということはあったんですけど、裏テーマとしてはバンドメンバーが僕のうしろで演奏して良かったと思ってもらいたいっていうのがありました。
もちろん今回のライブメンバーは、僕の専属バンドではないですし、いろんなアーティストのうしろで表現する方々なので、その人たちが“ああ、川崎鷹也のうしろでやれて幸せだった”と、この先、何年後かに振り返ったときに思ってもらえるステージを作りたいっていうのが強かったんです。だからこそ自分ひとりでは出せない実力が、たぶん出せたのではないかなとは思いますね。
──弾き語りと違って、演劇や舞台で言うところの“座長”になるわけですしね。
川崎 そうですね。背負ってるものがやっぱり違いましたね。弾き語りは自分自身で責任を負っているので、たとえミスしても自分だけで完結するんですけど、バンドスタイルだとそうもいかないですからね。もちろん、僕がコケたところで演奏が止まる方々ではないし、まったく心配はしてなかったんですけど、ひとつのチームとして、バンドとして表現するのは簡単なことではないので、そこが難しくもあり楽しくもあり……みたいな感じですね。

──アマチュア時代からバンドは?
川崎 組んでいた時代もありましたね。5ピースで、僕はギターを持たないピン・ヴォーカルです。半年ぐらい活動して、方向性の違いで解散しました。
──東京公演は『カレンダー』からバンドアレンジの楽曲を中心にセットリストに入れていましたが、弾き語りも当然あって。そのバランスはどう取っていこうと考えましたか?
川崎 もちろん振り切って全曲バンド楽曲にすることもできたのですが、僕のこだわりとして“アコギ1本でどこでも戦える状態にしたい”っていうのがあるので、やっぱり弾き語りは何曲かはやりたいなという思いがあって。その中で、弾き語りで表現したい曲が本編で3曲、アンコールで1曲あったという感じですね。
──弾き語りでやりたい曲のほうが先に決まっていて、それをまとめてコーナー部分を作ろう、みたいな?
川崎 はい。弾き語りは僕の自由にできる唯一の場所なので、好きにその場で決めてもいいですし……それは困っちゃうな、スタッフさんが(笑)。
──実際にニューアルバムの曲をライブで演奏してみて、何か感じた部分はありますか?
川崎 どうしても弾き語りだとラブソングやバラードだったりと、“聴かせる”っていう感覚が強いんですよね。いくらストロークでジャカジャカする曲でも、どうしたってそこの“伝え方”みたいなところの考え方がバンドとは違っていて。バンドの場合だと音で楽しんだりとか、単純に聴いていて身体が揺れたりとか、頭が動いたりとかっていう楽しみ方ができるのがお客さんを見ながらすごく自分で感じていました。(今まで弾き語りでやってきた曲も)バンドスタイルのほうが楽しめる曲があったり、逆に“あの曲は弾き語りだったときのほうが伝えられたな”とか、いろんな学びがありましたね。
──今後に活かしていける部分が貯まってきているところなんですね。「ヘイコウセカイ」のようなちょっと速めの8ビートっていうのは、「光さす」以来だと思うんですけど、やはりライブ映えしますよね。
川崎 そうですね。やってて楽しかったですし、マスク越しではありましたが、お客さんの表情が明るくなるのもわかったので。ライブシーンを想像してあの曲を書いているので、良かったですね。何か答え合わせができた気はします。
──「光さす」のときもそういうイメージだったんですか?
川崎 そうです。あれもバンドでやるイメージで書いてますね。

 メールマガジンを購読
メールマガジンを購読