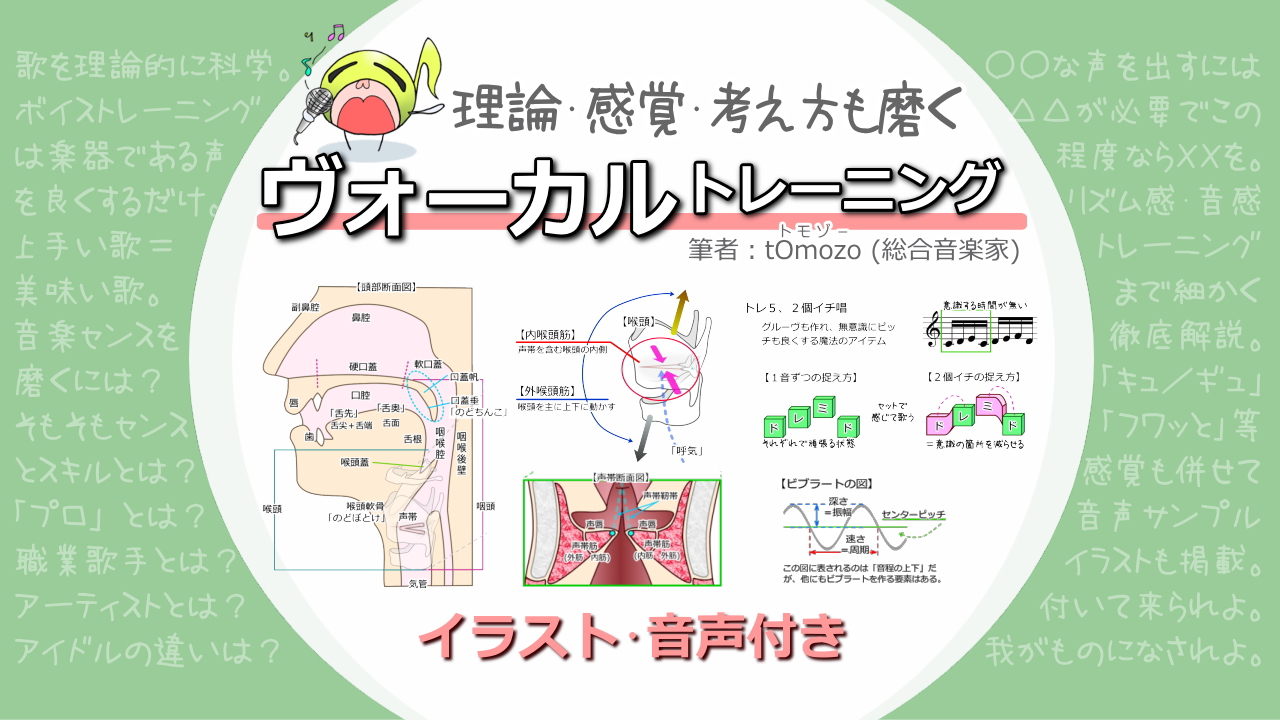インタビュー:藤井 徹(Vocal Magazine Web)
音楽評論家のスージー鈴木が著書『平成Jポップと令和歌謡』(彩流社)を上梓した。本書は『東京スポーツ』紙で好評連載中の「オジサンに贈るヒット曲講座」から、2016年4月の開始から2020年末までの230回分を編纂したもの。連載中に平成から令和へ元号を跨いだこともあり、特に加筆された部分で、現代日本における“大衆音楽”の流れを軽妙かつロジカルな論理で展開してくれている。
今回のインタビューでは、氏が唱えた“平成Jポップ”、“令和歌謡”的な音楽について、また、本書で取り上げられているヴォーカリストを中心に、じっくりと話を聞いてみたいと思う。
星野源がその確信を勇気づけてくれた。
──本書は『東京スポーツ』紙で連載中の「オジサンに贈るヒット曲講座」をまとめたものですが、連載タイトルを読めばコンセプトは明快ですね。
スージー 明快です。初めにオーダーを受けた時は“イヤだなあ”と思ったんです(笑)。(『週刊文春』で連載されていた)近田春夫の『考えるヒット』の異常な筆圧を見てきたので。“つまんない音楽も多いだろうし、自分にできんのかなあ”って部分で(笑)。でも、一応5年間、走り切ってます。
──マーケティング的な話ですが、読者のペルソナをどのあたりに定めていました?
スージー そうですね。今でもそうだと思いますが、基本的に日本の最新ヒット曲っていうのは、“若者だけ”を狙っているんです。連載の最初はゲスの極み乙女について書いたんですけど、“これは自分にも向けられていないし、周りの50代でこれを聴いて喜ぶ人はいないのかな……”と思いながらも、でも気持ちの中で、いやいやそうとも限らないぞと。これからジジイも増えていくんだし、平均年齢も50代手前になってきてるし、音楽業界自体もオヤジとかをオバサンとかを狙っていかないといけない。
だとしたら、“絶対これから出てくる音楽は、我々に向けたものになっていくだろう”ということで、初めはちょっと獣道に入る感じでしたけど、最近は私の周りでも、やっぱり米津玄師とか歌う人間はいますし、King Gnuなんかは絶賛されています。具体的なペルソナは見えていなかったけれど、“ゆくゆくはこういうヒット曲にまみれる50代が出てくるんじゃないか”という確信が、実は最初からありましたね。
──なるほど。その確信をもとに選曲を含めた方向付けをしていこうという感じだったのですね。
スージー より具体的に言うと星野源の登場ですね。僕は自分のサイト(『週刊スージー』)で、誰にも求められてないのに毎年自分の中でレコード大賞を決めているんです(笑)。そこで、連載開始前年である2015年のレコード大賞を星野源の『Yellow Dancer』にしたんですよ。非常に若者が盛り上がっている、と。でも、本当に同時進行で僕と同世代が盛り上がったんですよね。明らかに自分が聴いていた細野晴臣の『泰安洋行』とか小沢健二の『LIFE』と同じ匂いがする。そういう意味では、星野源がその確信を勇気づけてくれた感じはありましたね。
──星野源さんが連載の進む道を照らしていた感じがあったんですね。では、連載で取り上げる曲の具体的なセレクト方法は?
スージー 毎週やってくるんでね、敵は(笑)。とにかくまずは『Billboard JAPAN Hot100』をチェックします。オリコンに比べてビルボードのチャートは非常に固定的で、ずっとベストテンに米津玄師「Lemon」があったりする(笑)。まずそこで突飛な動きをしている“謎の名前”とか“謎の曲”とかに食いつくんです。そこには多分ネタがあるはずだから。どうしても候補がなければ自分の趣味のドラマの主題歌とかですね(笑)。
基本的には、すでに知っている人の新曲よりは、なんか変な名前の見たことも聞いたこともないアーティストが、TikTokなんかから出てくると書きやすいんですよ。例えば瑛人の「香水」の動きを見たら、“いったい何が起こってるんだろう?”って。
──東スポ読者のオジサンたちを置いてきぼりにしないよう、スージーさん独特の距離感の中に収めていて、さすがだなと思いました。
スージー YOASOBIなどが代表的ですけど、見てくれとか立て付けはまったく新しいわけです。『monogatary.com』という小説サイトがあって、ikuraとAyaseというメンバーがいて……など、新しくって、それはオジサンには付け入る隙がないんですよ。実際、私も最初にYOASOBIについて書いた時は、“何か得体の知れないもの”と書いてるんですが、聴き込んでみると、どこか過去の音楽のリスニング経験と繋がるんですよ。コード進行としてF-G7-Em-Amを多用している、と。
──音楽的な類似性を見つけたんですね。
スージー マキタスポーツは“未練進行”、私は“「卒業写真」進行”などと表現している、なぜか日本人が好きすぎるコード進行がありまして。実はYOASOBIという得体の知れないブランドの中に、我々世代と変わらない胸がきゅんとするコード進行が多用されている。
そうであれば同様の経験をしているはずの読み手のオジサンにも繋がってくるはずだと。得体の知れないものに食いつきながら、その中で自分のリスニング経験と繋がる共通点、汎用性を探していく作業と言いましょうか。基本的には、そこに一般性が生まれるというセオリーでやってきたつもりです。
令和ヴォーカルはマイルドな響きになっていく。
──今回は『平成Jポップと令和歌謡』ということで、平成と令和時代におけるヴォーカル・スタイルの変化という点を中心に話していただきたいなと思っています。
スージー この本では、90年代以降の日本の大衆音楽におけるヴォーカルの変化を、期せずして後天的に分析したような作りになったんですけど、一番大きいのはCDからサブスクへの変化だと思いますね。これまでシングルでも5〜6分は当たり前だった曲の長さが、今は3分台ほどの短い曲が増えてきています。
そのぶん構成もA〜Bメロ、たまにCメロぐらいで終わる簡素なものものになる。あとは転調して難しいコードを使いまくるドラマチックな構成というものがJポップ的ですけど、その点でもシンプルなものになっていくだろうと思います。
──ヴォーカリストの声や歌い方については?
スージー この本の中で触れている人だと米津玄師、藤井 風……。女性ではAimerやmilet……。感覚的な言い方をすると、ハスキーで高いキーでシャウトするヴォーカリストよりは、マイルドで丸い音になっていくと思います。バック演奏もアコースティックの生音のシンプルな形で、ある意味では昭和歌謡回帰になっていく。
そんな中で、例えば桜井和寿(Mr.Children)のような、CDという“倍音のキラキラした響き”で輝くスタイルから、スマホ経由のヘッドフォンで聴いて映えるような“マイルドな響き”に変化していくんじゃないかなと思ってます。あくまでこれは個人的な仮説ですけどね。
──その転換期が、ちょうど本書に収められた5年ぐらいの間に起きてきたということですね。
スージー さらに言えば、そこにカラオケっていう登場人物がいて。平成Jポップの大層なメロディは転調が多く、すごく高いところまでピッチがのぼっていくような音楽で、それをカラオケで再現する嬉しさがあるんですよね。具体的に言うなら米米クラブの「浪漫飛行」を歌っていて、《♪忘れな〜い〜で〜》になったところで、“キターッ!”っていうね(笑)。
カラオケによって“再現音楽”としてのJポップが発達したんですけど、今は家でシングルCDを何回もトレーに乗せて練習して……という気合がなくなって。なんとなくスマホから流れてくる圧縮されたしょぼい音質の再生環境の中では、米津玄師みたいな声のスッと入る感じが、これからのヴォーカル市場に影響を与えていくと思う。これも仮説ですけどね。
──平成は31年4月までですが、スージーさんが“平成Jポップ”と指しているのは、おもに1998年頃までと考えていていいですか?
スージー はい。具体的に言えば1998年のCD市場のピークとした、その裾野くらいまでです。だから平成前半ですよね。
──90年代初頭、世の中はバブル崩壊で苦しんでいて、さらに天災、凄惨な事件が続きました。そんな中で音楽業界だけがバブル景気だったという。その中で、“がんばろう系”の歌詞を持つヒット曲が多く生まれました。歌い方も含め、求められたのは時代の流れでしょうけど、それがビジネスになったっていうところですよね。
スージー そうですよね。多くのレコード会社が都内に自社ビルを作り……。テレビドラマやCMからのタイアップでヒット曲が作られ、みんなが行列を作ってそれをメガストアで買い、カラオケで歌ってというようなピークは98年。音楽市場が爆発することは、まことに好ましいところですけど、音楽の聴き方がちょっと機能主義っていうんですかね。
歌って気持ちいいものとか、歌のメロディやコード進行、歌詞の内容っていうのが、カラオケボックスの中では非常に機能的でメリットがあった。“明日も忙しくなるけど、頑張っていこうぜ!”みたいな。そういう機能を求めていったものが、ここで言う平成Jポップの一番端的な形ですね。

 メールマガジンを購読
メールマガジンを購読