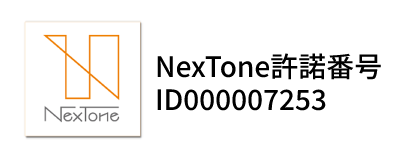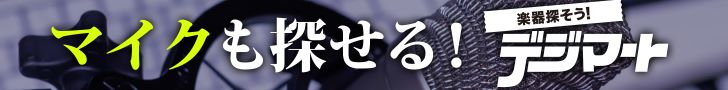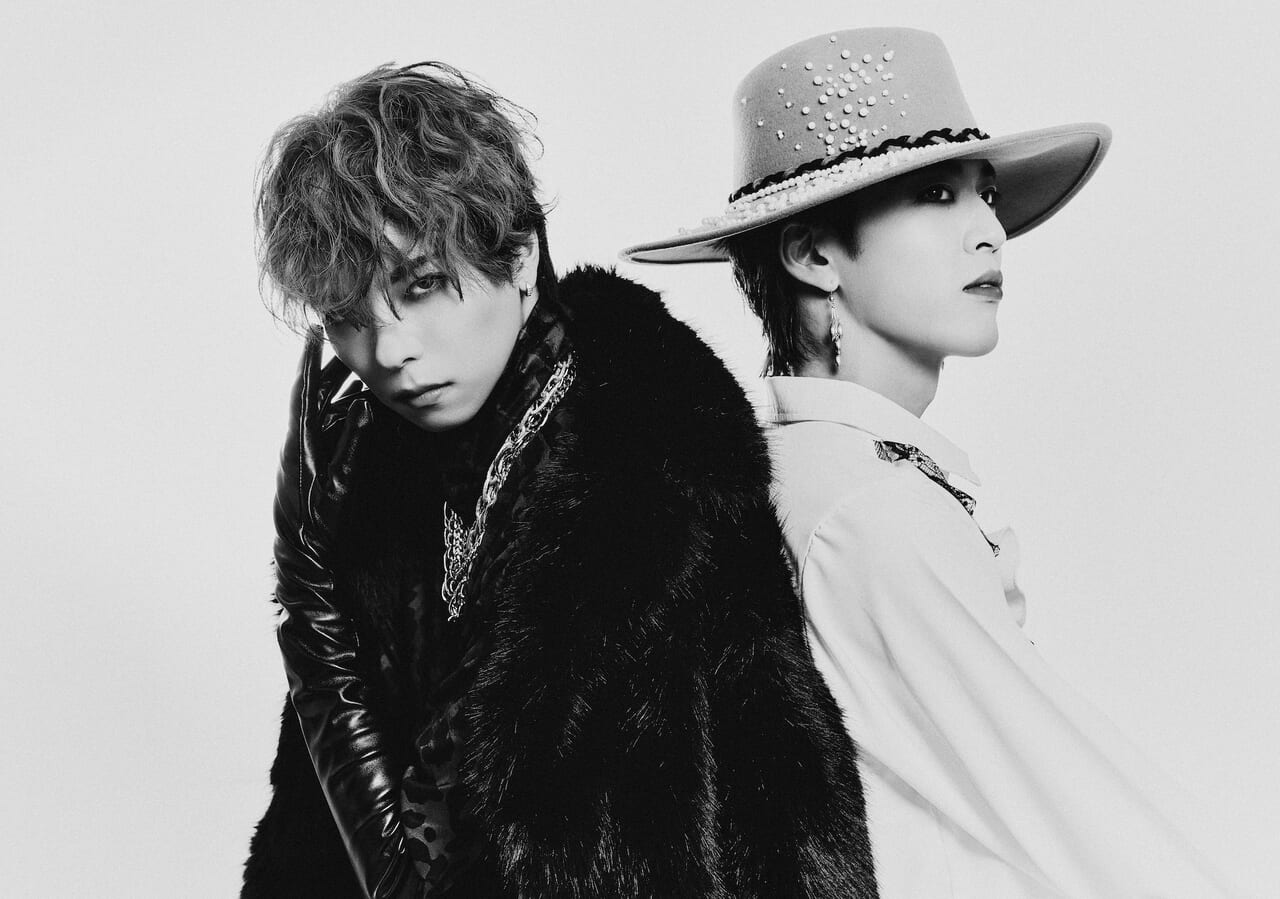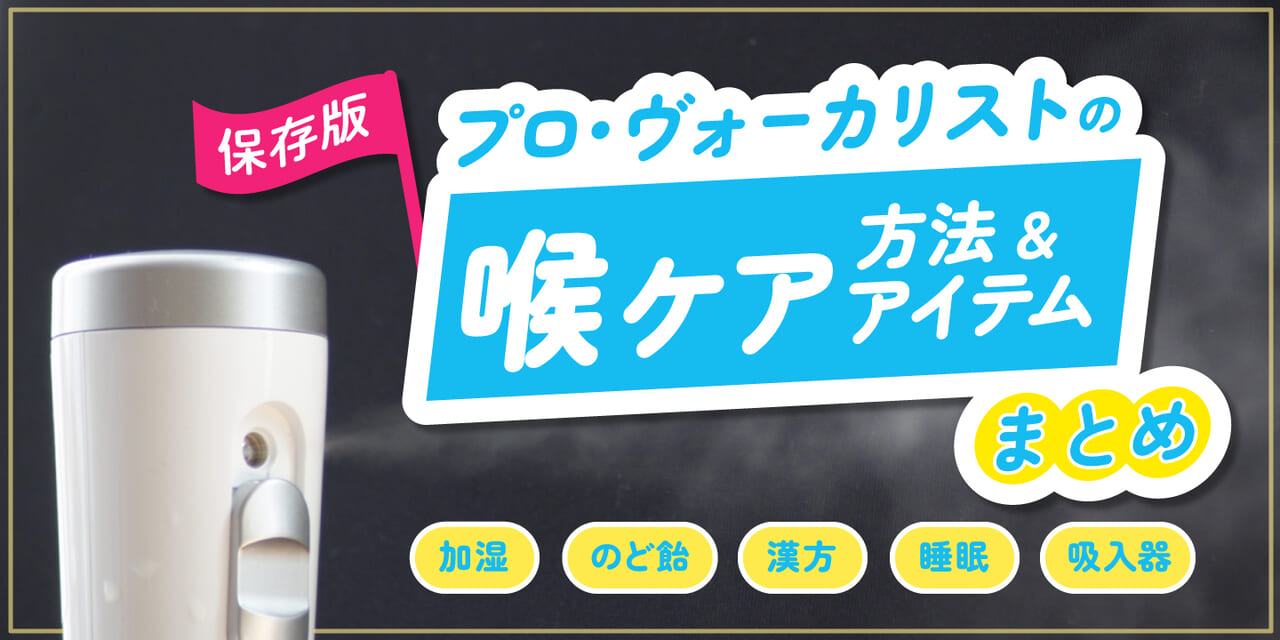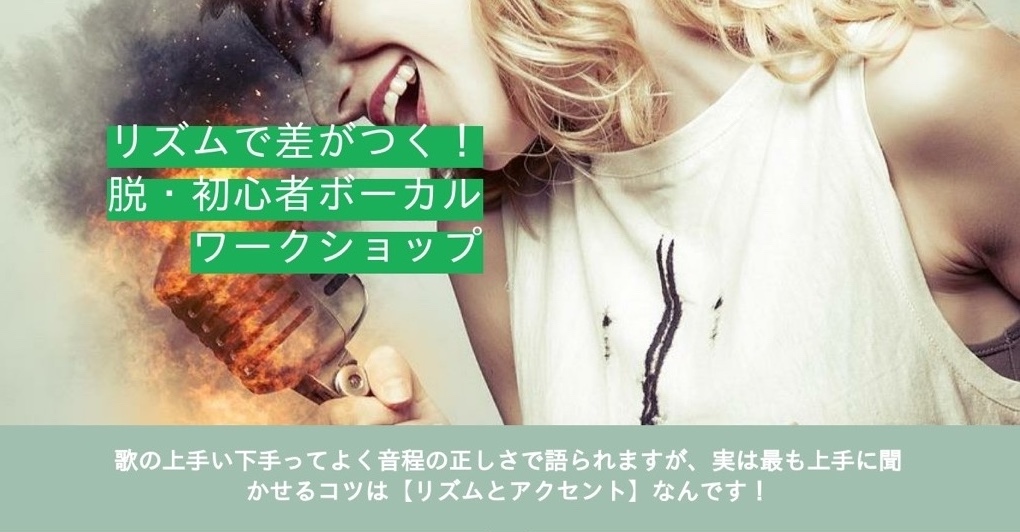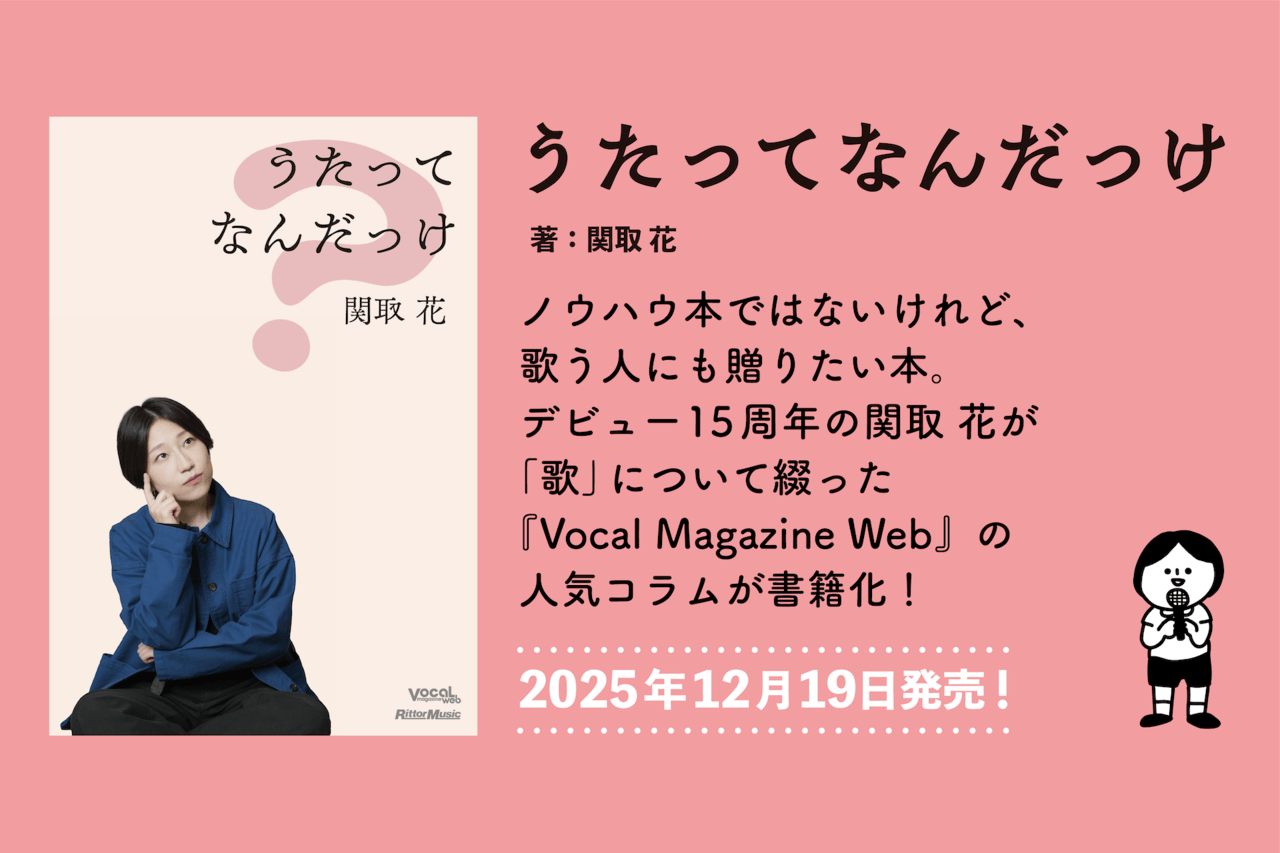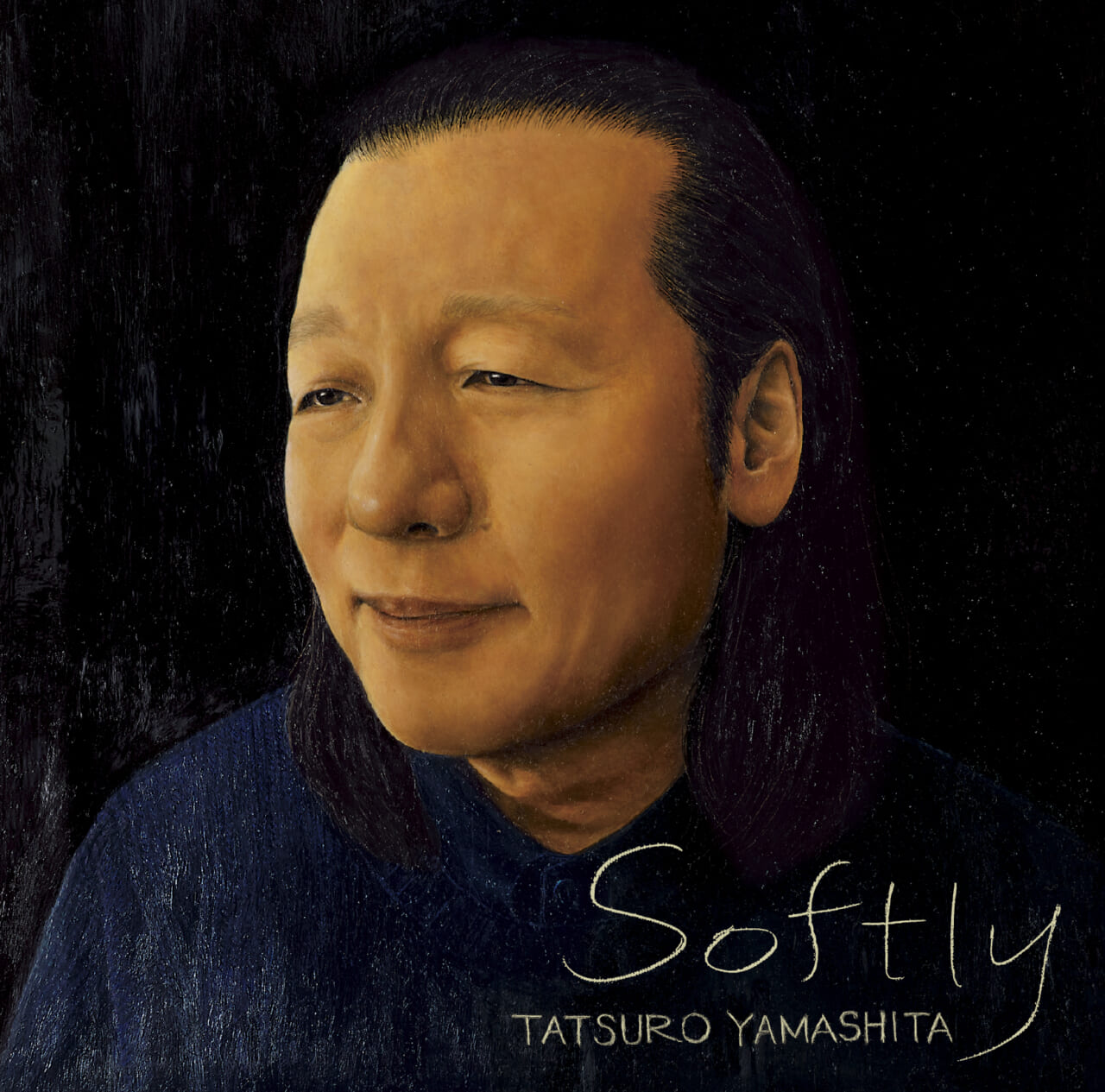取材・文:藤井 徹(Vocal Magazine Web)
詩吟と知らずに聴いてカッコいいと思わせたい

──次は「ミトコンドリア」です。タイトルがなかなか面白いですね。
鈴華 私的にも目の付け所がいいなと気に入ってます(笑)。
──ダイエットや美容へ踏み出そうとする女性の心意気を、細胞から湧き出る活力の視点を入れた応援歌みたいな曲ですね。
鈴華 これ、全然等身大の私の歌です。ある日、うちの母親が「これね、ミトコンドリアに効くんだわ」ってサプリメントを持ってきたんです。「ミトコンドリアに? ほぉ、もうちょっと聞かせて」みたいなことが実際あって(笑)。細胞活性化すると肌艶も良くなって、みたいなことを母から聞いて、やっぱり面白かったわけですよ。ミトコンドリアか、気にしたことなかったなと。でも、“美容のことを考えると、身体の中から”みたいな話って女の子だったら絶対みんな知ってるし、“糖質制限してみよう!”も絶対に経験ある。
けっこう私って昔から「伝統ある家系でお堅くて、あんまり病んだりしないんでしょ」って勝手にイメージを持たれがちなんですけど、全然そんなことなくて。普通の女の子だし、病むし。この自暴自棄から脱出するためにジムのWeb入会だけ一旦入力してみよう、みたいなことも全然あるんです。その等身大の自分を、共感できる女子に向けて書いた曲で、“女の子は誰もが磨けば光放つミトコンドリアを持っていて、誰もがお嬢様だよ”っていうメッセージですね。
──応援歌でもあるし、すごくパワーをもらえますよね。このアルバム用に書き下ろしたんですか?
鈴華 私、曲のストックがすごくたくさんあるんですが、まずは“アルバムにこういう曲が欲しい”って構成を組み立てるんです。“ちょっとJ-POP寄りで女性に女性として寄り添う系で、ライブではタオル振りたい!みたいな楽曲が必要”となったときに、新曲で書き下ろすこともありますが、この曲はワンコーラスだけ作ってあったものから完成させました。
──そして「Bloody Waltz」ですね。こちらはタイトルが示すように、3連のリズムに乗せた妖艶な世界観を持つ楽曲です。
鈴華 これはバンパイアです。
──ワルツですけどメロディが自由で、そこが和テイストな響きを醸し出している要因のひとつかなと感じます。
鈴華 出だしは4拍子で、ここはとにかく“和”寄りなんですけど、《トン!》っていう一発をきっかけにサビで3拍子のワルツに切り替わります。拍子の変化で場面も変化し、普段のときとバンパイアになったときの切り替えの世界観を表現しました。
──そうだったんですね。リズムの頭を見失いそうになるのですが、歌う際のアドバイスをください!
鈴華 3拍子になった瞬間ですね。よくドラムを聴いて歌ってください(笑)。3拍子と言いながら8分の6拍子なので、大きなふたつの3拍子と取ってノレたらすごく気持ちよく歌えると思います。歌い始めの《夜に》という(音程が)下のところから来て、3拍子で《恍惚に》と高音から入ってくるので、この振り幅も歌えたら楽しいです。私もライブのリハをしていて、この曲めちゃくちゃ楽しいですから、ぜひカラオケでも歌ってほしいですね。
──7曲目は「SHIGIN BEATS-大楠公-」で、こちらはEDM+詩吟という楽曲です。鈴華さんは今年「吟道鈴華流」を創流されましたし、今回の作品に詩吟の楽曲を入れることに意味がとてもあったと思います。それについての想いを聞かせてください。
鈴華 よく「伝統」っていう言葉を使いますが、実はこの熟語自体が新しいものだと私は聞いたことがあって。昔は「伝統」って言葉すらなかったと。では「伝統って何なの?」って言ったら、「古いものを守ること」だと思いがちですけど、そうではなく、「昔からあるものを、その時代に合わせて変化しながら受け継いで続けていくこと」っていう意味だと私は思っていて、興味を持つ人がひとりもいなくなってしまったら、単純に消えてなくなってしまうんですよね。だからこそ、今の時代で興味を持っていただける提案はしていくべきだと思っていて。本来の型を崩すという意味ではなく、例えばEDMを好きな人が聴いていて「なにこの裏で鳴ってる和風っぽいやつ、めっちゃカッコいいじゃん!」と思えたらこっちのものですけど、「それが実は詩吟だった」っていう導入になりうるものだと思っています。本来詩吟ってリズムはないもので、うまくテンポの中にはめて詩を歌うっていうのは、詩吟の業界の中ではないことなんです。だけど、そういうこともできるよっていうのがこの時代に生まれても、別に私はいいと思っているので。
私はいろんな意味でこの曲をやっているんですけど、アルバムの中としては箸休めと思いきや、耳の切り替えポイント、ド真ん中にあるんです。これは「私の詩吟を中心にできあがっているアルバム」という立ち位置の意味がひとつと、「これを詩吟と知らずに聴いてカッコいいと思わせたい」という仕掛けの意味がひとつ。詩吟の業界に対しては、いろんなミクスチャーをするのが日本の音楽らしさであり、もちろん「これは邪道だ」と思うこともあるかもしれませんが、こういった嗜み方がこの令和の時代に存在したという、選択肢のひとつとしての作品があっても面白いかなって。そんな意味が込められています。
──まさに究極のミクスチャーですよね。取り上げた詩についても教えてください。
鈴華 この詩を書いている徳川斉昭は水戸藩の9代藩主だった人です。斉昭が残した詩には私も子供の頃からたくさん触れてきていて、自身の音楽で取り上げるならば、やっぱり自分の故郷の人が書いた詩にしたいなと。あと、“今の時代では、あまりこの概念ないよね”っていうようなものを詩吟から学ぶことも多いのですけれども、これは(戦国時代の武将・楠木正成の)忠誠心を(斉昭が)称えた詩になっていて。もちろん「時代に合ってないよ」と言われたらそれまでなのですが、「そういう感覚を持って生きていた時代もある」というところを私は大事に思い、この詩を選んだという部分もありますね。
──徳川斉昭が詠んだ詩は、他にも有名なものがあるんですか?
鈴華 けっこうありますね。例えば「弘道館に梅花を賞す」という詩があります。水戸に弘道館という場所が今もあるのですが、そこは藩士たちが勉学に励むためにと徳川斉昭が作った道場なんですね。すぐそばに日本三名園のひとつである偕楽園という庭園があり、弘道館や偕楽園についての斉昭の詩も残っています。水戸の詩吟の流派は大会の始めに、みんなで「弘道館に梅花を賞す」を合吟するんですよ。私は5歳の頃からそれをやっていますし、故郷の風景が今も残っている場所があるので、長く親しんでいる徳川斉昭の詩が良いなと思ったんですが、こういうEDMに弘道館はあまり合わないなと思って(笑)。“きれいな梅の花を見ている”とか、ちょっと風景も入ってくるんで。風景詩、抒情詩、戦ものや回顧しているものだとか、たくさんあって。だけどこの《豹は死して皮を留む》で始まる詩はEDMにピッタリだなと思うし、やっぱり曲としても合う詩を選んでます。
──EDMのトラックは和楽器バンドの盟友・町屋さん(クレジットは桜村眞)が作っています。どんなやり取りで進みました?
鈴華 「詩吟のことはあまり気にしなくていいから、これくらいのテンポ感で、EDMで」って感じでスタートしました。私が琴のパートを打ち込みで作って、詩吟をこういう風にはめるっていう流れの中で、「ここは多いから削ろう」とか、ちょっとパズルっぽく作っていきました。やっぱり町屋と作るのはラクですね。

 メールマガジンを購読
メールマガジンを購読